福岡の弁護士が 相続のお悩みを 親身になって解決します
- 空港線空港線16番出口徒歩3分
- 天神大牟田線西鉄福岡(天神)駅徒歩約10分
- 七隈線天神南駅 5番出口徒歩約3分
-
来所相談30分無料
-
通話料無料
-
年中無休
-
24時間予約受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

来所相談30分無料
通話料無料
年中無休
24時間予約受付
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
「自分が死んでからのことは考えたくない。」、「自分の子供たちは仲が良いから心配ない。」、「自分の意思は子供たちに伝えているから大丈夫。」、「財産なんて残らないから争いようがない。」などと相続について考えることを先送りにしていませんか。
「相続は、死亡によって開始する。」(民法882条)ので、相続が発生した時には、ご自身はこの世におらず、相続人達を叱りつけることもできません。子供たちの配偶者や、大きくなった孫などの事実上の利害関係人が口を出すことで揉めることはよくあります。
「まさか・・・」と思われるかもしれませんが、相続紛争の相当数は、「まさか・・・」という事案です。 「終活」という言葉が浸透しつつありますが、まだまだ、相続の話しはタブー視される傾向にあります。お気持ちは理解できるところですが、相続争いが起こった責任は、相続に関する話を先送りにした被相続人と相続人の双方にあります。相続は、相続人が遺産をどう分けるかという発想になりがちですが、相続とは、被相続人の生前の意思を実現する手続きだと考えるべきです。
面倒かもしれませんが、相続を知り、親族間(推定相続人に限らず)で相続について話す機会を作って下さい。

民法では、法定相続分(民法900条、901条)に反して遺言で共同相続人の相続分を定めることができるなど(民法902条)、被相続人の意思である遺言を相続人の相続権より優先する仕組みになっています。厳密には相続とは、被相続人の死亡時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継することを意味し(民法882条、896条)、遺言によって相続人以外に対しても、包括又は特定の名義で財産の全部又は一部を処分できる遺贈(民法964条)とは異なるものですが、実務上も遺贈を含めて被相続人の財産の承継について相続と呼ぶので混乱しがちです。
法定相続が原則で、遺言や遺贈は法定相続の内容を変更させるというイメージが強いかもしれませんが、まずは亡くなった方の意思を尊重し、遺言がない場合に法定相続分などの規定に従い相続するという仕組みです。 遺言を残すべきだと思いませんか。
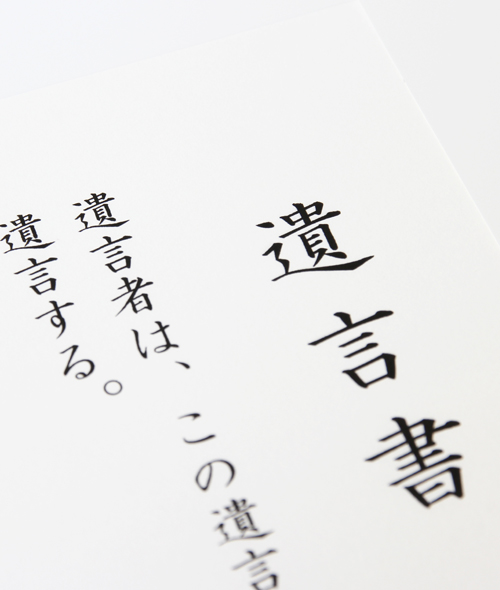
相続の準備01
遺言書を 作成したい
遺言は、死亡の危急に迫った者の遺言など特別な例外を除き、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならず(民法960条、同967条)、それぞれ自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と呼ばれます。
自筆証書遺言について、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならないと規定されているなど、遺言の種類ごと定められたルールを守らなければ無効になります(民法968条など)。せっかく遺言を残しても、法的効果が認められなければ意味がないので注意が必要です。この点、公正証書遺言は、公証人が関与して作成されるので、形式面の不備で無効となることは考えにくく、お薦めします。
内容によっては、相続人の遺留分を侵害する場合など後の紛争が予想されることもありますが、あまり深く考えずに、「あの人にはなるべく遺産を残したくない。」、「あの人には土地を守っていって欲しい。」、「子供たちに仲良くして欲しいから紛争にならないよう公平な内容として欲しい。」など、まずは専門家に思いを伝えてみて下さい。きっと、思いを実現する方法を一緒に考えてくれるはずです。遺言がかえって紛争の火種になることもありますので、専門家のアドバイスを踏まえ遺言書を作成することをお薦めします。

相続の準備02
財産が どれくらいあるか 残しておきたい
財産を把握することは重要です。相続では、相続開始時(被相続人の死亡時)において、被相続人の財産に属した一切の権利義務が承継されます(民法882条、896条)。将来、被相続人になる方としては、自分の財産を把握しておかなければ、適切に遺言を残すことができませんし、相続紛争が生じるリスクを把握することもできません。また、プラスの財産だけなく、借金などのマイナスの財産も相続される以上、全ての財産を把握できていなければ、相続が発生してから相続人が慌てることになりかねません。
具体的には、財産の全てを標目ごとに、内容や評価額、関係者の連絡先などをまとめた、財産目録を作ることが良いでしょう。まずは、手書きでもいいですから、財産目録を作るところから始めて下さい。ご自身で作成することが面倒だ、難しい、不安だという場合には、弁護士など専門家に相談してみてください。財産目録作成はもちろん、その後の相続準備についても力になってくれるでしょう。

相続の準備03
相続税対策を 作成したい
遺産が多くあると、相続人達に相続税が発生します。遺産に十分な現預金があれば、相続人で話し合って、遺産を利用して相続税を支払うことも可能です。しかし、不動産しかない場合はどうでしょう。遺産に現預金が少ないと、納税するために遺産を処分せざるを得ないということもあります。相続税は相続開始から10か月以内に申告しなければなりませんので、49日を待って親族で遺産分割の話を始めたりしていると、あっという間に申告期限間近になり、大切な不動産を安く売却するしかないということもあり得ます。
相続税には非課税枠があるので、非課税枠に収まるよう生前に誰かへ贈与するなどして財産を減らしておくことも考えられますが、相続税を回避できたとしても、贈与税が生じることもありますし、相続人に譲る(贈与する)場合は、特別受益に該当することで紛争の火種になります。 遺産を誰が相続するかによっても相続税の額は変わりますし、遺産は順次相続されていく可能性があるものですから、二次相続時に相続税が幾ら発生する可能性があるのかも踏まえて遺言や遺産分割を行うことで相続税のトータルを減らすことができます。
このように、相続は、相続紛争の予防の視点だけでなく相続税対策の視点も踏まえて準備しなければなりません。
弁護士に依頼する最大のメリットは、生の相続紛争を解決してきた経験をもとに、遺言書の形式のみならず、それまでの人間関係や、遺言者の望みを踏まえてアドバイスをもらえることです。公証役場へ行けば、公証人がアドバイスをくれますが、詳しく事情を聴き取り、遺言者の要望を実現しようと親身になってアドバイスをくれるわけではありません。
また、遺言は遺言能力があるうちに作成しなければならず(民法963条)、遺言者が亡くなった時にその効力を生じるものなので(民法985条)、遺言書を作成した当時の財産状況や人間関係と現在のそれらが異なることはよくあります。遺言者は、遺言の内容を変えることができますので(民法1023条~1027条)、随時、遺言内容を修正することも考えなければなりません。その際、状況を良く把握している専門家に継続的に相談できれば、これまでの流れを踏まえた適切なアドバイスを受けることができます。
相続紛争を多く扱ってきた弁護士であれば、大体、相続人間でどういった主張がされるか分かります。例えば、「認知症で判断能力が無かったはずで、遺言書は兄の言いなりで書かされたものだ。」、「面倒を見ていることをいいことに預金を使い込んだ。」、「生前、援助を受けていた。」、「私が世話をしたのだから多く遺産を貰うべきだ。」といったものは定番の主張です。弁護士であれば、そういった主張がなるべくされないよう、経験に基づいた遺言書を作成できることができます。
01
もし遺言書がなかった 場合の遺産分割で スムーズに対応できる
02
遺言書作成を代行して もらうことができ不備のない 遺言書が作れる
03
内容に不満がある場合に 解決策や対処法を 考えてくれる
04
遺言内容による トラブルの早期解決
など
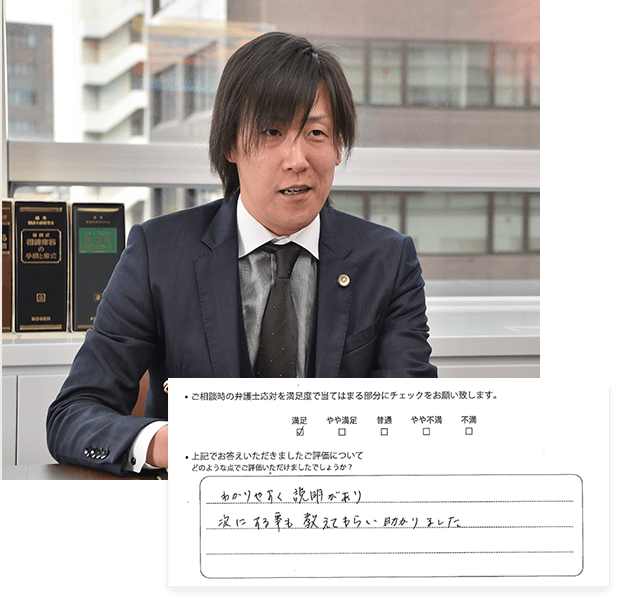
満足
わかりやすく説明があり次にする事も教えてもらい助かりました。
来所法律相談30分無料 相続のお悩みなら私たちにお任せください。
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
Case01
何が相続の対象になるのか知らなければ、相続放棄すべきか判断がつきません。相続放棄の期限は3か月なので、まずは、相続財産として何がいくらあるのか知ることから始めることになります(相続財産調査)。並行して、誰が相続人なのかも調べます(相続人調査)。遺言で法定相続人以外の者が遺贈を受けることとなっていたり、法定相続分とは異なる遺贈がされている可能性もあるので、遺言の有無も確認しなくてはなりません。その後、相続人間で具体的な遺産の分け方について協議することになります。
公正証書遺言は、相続人が公証役場へ照会し、謄本の交付を請求すれば内容を確認できます。秘密証書遺言は、公証人が関わって作成されていることから、公証役場へ照会すれば有無について確認することが可能ですが、内容を確認するには見つけ出すしかありません。自筆証書遺言については、探し出すしかありません。多くが自宅に保管されていると思いますが、弁護士や司法書士に預けている場合もあります。また、法改正により、自筆証書遺言の保管制度が新設されたので、改正法施行日である令和2年7月10日以降は、法務局で保管されていることも考えられます。
遺言が見つかった場合、秘密証書遺言や自筆証書遺言などは、裁判所で検認の手続きをしなければなりませんので、開封しないよう注意してください。
被相続人に養子や認知した子、前妻との子がいる場合など、思わぬ相続人がいることがあります。戸籍の身分関係欄の記載には、戸籍の改製や他の戸籍への入籍、本籍の移転(転籍)に際して移記されない事項もあるため、相続開始時の戸籍(除籍謄本)だけでは判明しない相続人が存在する可能性があるのです。このため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取得し、子(養子含む)や兄弟姉妹、代襲相続人などの相続人を確認することは不可欠です。
相続人が判明したら、次に、相続人の連絡先を知る必要があります。どなたか事情を知る人がいれば、教えてもらえば済むのですが、所在や生死すら不明だということもあるでしょう。戸籍の附票を取得すれば、戸籍に記載がされている者の住民票上の住所を知ることができますが、その住所地に既に居住していないこともあります。探したが所在が分からないという場合には、不在者財産管理人の選任や失踪宣告の審判を申し立てることを検討しなければなりません。
稀に、夫が亡くなった際に、妻が妊娠中ということがあります。相続開始時に子が出生していなくても胎児には相続権が認められ、死産した場合には相続人でなかったことと扱われます(民法886条)。実務上、胎児の段階で遺産分割協議は出来ないので、通常は、出生を待って遺産分割協議を行うことになります。なお、遺産分割に際して、妻と出生した子供の利益が相反する場合には、裁判所に子の特別代理人を選任してもらい、特別代理人が遺産分割を行うことになります。 認知未了の子は、父の死亡の日から3年以内に検察官を相手方として認知の訴えを提起し(死後認知の訴え)、これが認められれば、法律上の子として相続人となります。
なお、法定の相続人であることが判明したとしても。相続欠格事由に該当すれば相続人になることはできません(民法891条)。推定相続人の廃除の審判が確定した場合には相続人から廃除されます。この場合は、直系卑属による代襲相続が発生します。他方、相続放棄の場合は、相続人とならなかったもの扱われ、代襲相続も発生しません(民法939条、同887条)。
相続放棄をするのか、どのように遺産分割協議をするのか、遺留分を侵害されているのかなどを検討する前提として、遺産の内容を把握する必要があります。生前、相続対策などで被相続人が財産目録を作っている場合や、成年後見人がついていて財産目録が作成されている場合であれば別ですが、正確に遺産の内容を把握されていないのが普通ですから、多くの場合、遺産の調査が必要になります。
不動産については、どういった不動産があるか明確であれば、不動産登記を法務局で取得して間違いないか確認することで足りますが、市町村長(東京の場合は都税事務所)へ名寄帳の写しの交付を請求することで、新たな不動産が判明することもありますので、一応、名寄帳を取るようにして下さい。なお、当該市区町村以外の不動産や法人名義の不動産、相続手続未了の不動産は名寄帳に記載がないので注意が必要です。
預貯金については、預貯金の通帳や預貯金証書があれば把握ができます。預貯金通帳や証書がなくても、金融機関から取引履歴や残高証明書をとることで把握できます。過去の取引内容から保険契約や有価証券などの他の財産について判明することも多いので、数年間の取引履歴を確認することは忘れないでください。相続税や贈与税などの税務面からすれば相続開始前3年ないし6年程度を把握することをお薦めします。
借金や保証債務なども相続の対象になることから、相続債務の調査も必要です。金融機関がわかるのであれば、借入金残高証明書の発行を求めることで把握できます。預貯金の取引履歴や、生前の様子などから、借入等の可能性のある金融機関へは問い合わせをすべきでしょう。信用情報機関から信用情報を取得することも有益です。
その他、被相続人が賃料収入を得ている場合には賃貸人の地位も相続しますし、個人事業を営んでいるのであれば、事業用資産も相続の対象になります。ゴルフ会員権(会員契約上の地位)や株式も相続の対象になりますので、これらについても調査しなければなりません。 相続財産調査は、思ったより手間も時間もかかる作業です。
Case02
相続法の規定ぶりからすると、法定相続分(民法900条、901条)に反して遺言で共同相続人の相続分を定めることができるなど(民法902条)、被相続人の意思である遺言を相続人の相続権より優先する仕組みになっています。相続の原則は、遺言がある遺言相続だと言えます。
そこで、まずは、遺言がある場合の遺言相続について記載します。
遺言は、死亡の危急に迫った者の遺言など特別な場合(特別の方式)を除き、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならず、それぞれ自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と呼ばれます。(民法960条、967条)。公正証書遺言については検認不要ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言などの遺言については、「遺言の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がいない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする。」(民法1004条1項)、「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することはできない。」(民法1004条3項)として、検認が義務づけられ、「検認の請求を怠り、検認を経ずに遺言を執行し、又は家庭裁判所外で開封をした者には5万円の過料に処する。」(民法1005条)とされ、過料の制裁まであります。また、相続人が遺言書を偽造や変造、破棄、隠匿すると相続欠格者となりますし(民法891条5号)、受遺者の場合は受遺欠格者となりますので(民法965条、同891条5号)、遺言を保管されていた方や遺言を発見した相続人の方は、検認を忘れないようにしてください。具体的には、相続開始地を管轄する家庭裁判所へ、遺言書検認申立書に遺言者の出生時から死亡時までの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本などの資料を添付して提出すると、裁判所で遺言書の開封、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などが確認され検認調書が作成されます。
なお、相続法改正に伴い「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(令和2年7月10日施行期日)が制定され、同法律に基づき法務局で保管される自筆証書遺言については検認が不要です(法務局における遺言書の保管等に関する法律11条)。
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます(民法1006条1項)。指定の遺言執行者がいないとき、又は亡くなったときは、家庭裁判所は利害関係人の請求によって、これを選任することができます(民法1010条)。
遺言による認知の届出は、遺言執行者がしなければならないなど(戸籍法64条)、遺言執行者でなければできない手続きもありますが、必ず遺言で遺言執行者定めなければならないわけではありません。遺言執行者が必要ない事案も多いと思います。遺言執行者は、遅滞なく相続財産の目録を作成し相続人に交付しなければいけませんし、相続人への報告義務など、相当程度の負担がある一方で、正当な事由がなければ辞任できないことから、その負担は軽くありません(遺言執行者に就任するかどうかは自由です。)。
遺言の執行に必要か否かを踏まえ、遺言執行者を指定するか判断することになります。前述の遺言認知などでは遺言執行者を定めておくべきですし、不動産を遺贈する場合には、登記義務者である相続人または遺言執行者と受遺者との共同申請で登記手続きをする必要があり、遺言執行者を指定しておくことで登記手続きをスムースに行えますので、遺言執行者はいた方がよいと思います。遺言の執行について紛争が予想されるのであれば、遺言の執行を取り仕切る存在として、弁護士などの専門家を遺言執行者に指定しておくべきでしょう。
Case03
遺言がない場合、相続人は、相続開始の時から、被相続人の一身に専属したものを除き、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属し(民法898条)、各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します(民法899条)。
法定相続人が複数いる場合には、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部を分割することができます(民法907条1項)。この協議を遺産分割協議と呼び、協議がまとまれば、通常、遺産分割協議書を作成し、登記手続きや預貯金の解約、払い戻し手続きなどを行います。有効に遺産分割協議をするには、共同相続人全員(包括受遺者や相続分譲受人がいればその者も含みます。)が合意する必要があり、共同相続人の中に共同相続人の子供(未成年者)がいたり、行方不明者がいれば特別代理人の選任や不在者財産管理人の選任といった手続きも行わなければなりません。
遺産分割協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。具体的には、遺産分割調停を申立て、調停でも解決できなければ裁判所の審判に委ねることになります。なお、共同相続人全員(包括受遺者や相続分譲受人などを含む)が参加する必要がある点は、遺産分割協議と同様です。
Case04
相続財産を受取りたくないという方もいるでしょう。「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純承認若しくは限定承認又は放棄をしなければならない。」(民法915条)とされ、相続人は、相続開始を知った時から3か月以内に相続放棄をすることができます。具体的には、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことになります。なお、3か月で判断できない場合には、家庭裁判に対して、相続の承認・放棄の期間を伸長することを請求することができます。遺産を全部又は一部を問わず処分してしまうなど、法定単純承認に該当する行為をしてしまうと、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
遺言による受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができ、遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力が生じます(民法986条)。但し、包括遺贈(遺言により無償で遺産の全部又は何分の1という割合で譲渡することをいい、包括遺贈を受けた者を包括受遺者といいます。)の場合、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するので(民法990条)、相続に関する規定が適用され、自己のために包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に遺贈の放棄をしなくてはなりません(民法915条)。具体的には、家庭裁判所へ包括遺贈放棄の申述を行います。
「相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務を承継する。」(民法896条)ので、負債についても相続することになります。そこで、負債を相続したくなければ、家庭裁判所へ相続放棄の申述を行うことになります。積極財産に比べて明らかに負債が多ければ、基本的に相続放棄をすることになるでしょう。なお、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとされ(民法939条)、代襲相続も発生しません。
負債がいくらあるか不明確で調査に時間を要する場合は、相続の承認・放棄期間の伸長を家庭裁判所へ申立て、熟慮期間を延ばしてもらいます。伸長期間は、相続財産の複雑さや所在場所などを踏まえ家庭裁判所が裁量により決定します。
調査した結果、相続財産で返済できる場合もあるでしょうし、実際に清算してみないと債務超過か否かわからない場合や負債額によっては負債も承継してしまおう思うかもしれません。そういった場合には、全て承継する単純承認や相続財産を限度とした有限責任を負う限定承認といった方法を検討することになります。なお、包括遺贈を限定承認することも可能です。
相続人は、被相続人に属した一切の権利義務を承継することから、債権者は法定相続人に対して請求してきます。相続放棄をしていれば、その旨伝えることで請求が止まることが通常です。債権者としては、次順位の相続人がいれば、その相続人に請求していくことになりますし、全ての相続人が相続放棄をした場合には、相続財産管理人の選任を申立て、相続財産から返済を受けることになります。
遺産分割協議は、遺言の効力、生前の使い込み、相続開始後の使い込み、特別受益、寄与分など様々な主張が入り乱れることが多く、一旦紛争化した協議をまとめるのは容易ではありません。ご相談があった際には、まず、特定遺贈や使い込みの有無などを踏まえた遺産の範囲の問題(遺産分割の対象の問題)と特別受益、寄与分といった事情を踏まえた相続分の問題(遺産の分け方の問題)とを分けて整理します。遺産目録や法定相続分・遺留分を付記した相続人関係図を作成し、これに遺言内容、特別受益、寄与分など情報を加えることで、遺産の範囲の問題と遺産の分け方を立体的に把握し、どの部分で意見が食い違うのか明確にしていただきます。

遺産分割協議がまとまらない原因の多くは、「私だけが亡母の介護をした。」、「兄は自宅購入資金を亡母から援助してもらった。」、「遺言は兄の言いなりで書かされたものだ。」、「亡母の口座にはもっと預金が残っているはずだ。」など、遺産の範囲の問題なのか、相続分の問題なのかといった整理をせずに各々の主張を資料の整理もせずにするからだと思います。弁護士は、資料をわかりやすく整理し争点を整理して進めるので協議が進むことも多いです。それでも協議が進まない場合には、家庭裁判所で調停を行いますが、調停は双方の主張を裁判官と調停委員で構成する調停委員会が言い分を聞いて調整する手続きなので、わかりやすく資料を整理して主張することが極めて重要になります。

民法では、兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められ(民法1042条)、遺留分権利者及びその承継人は、受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額請求ができます(民法1046条)。改正前は遺留分減殺請求と呼ばれていたものです。
兄弟姉妹以外の相続人が遺留分権利者に該当します。具体的には配偶者、子や子の代襲相続人、直系尊属が相続人となった場合です。もっとも、被相続人からの包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するとされていますが(民法990条)、遺留分が認められませんので遺留分侵害額請求もできません。他方、遺留分権利者から相続分の譲渡を受けた者は、遺留分権利者の承継人として遺留分侵害額請求権が認められます。自身の遺留分を認識しているか否かは消滅時効の成立には関係がありませんので、知らずに遺留分侵害額請求権を失ってしまわないよう注意して下さい。
遺留分権利者の方から「遺留分はいらない」と念書を書いたが大丈夫でしょうかとご相談を受けることがありますが、相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要ですから、相続開始前の放棄であれば無効なので安心して下さい(民法1049条1項)。なお、遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響しません(民法1049条2項)。
遺留分で一番悔しい思いをされるのは消滅時効だと思います。「遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも同様とする」(民法1048条)とされており、遺留分侵害額請求権は1年間の消滅時効にかかります。1年という期間だけでも短いですし、葬儀や遺品整理などしているうちにあっという間に1年が経過します。受遺者や受贈者に対して遺留分侵害額請求の意思表示さえすれば、消滅時効は中断しますので、遺留分を侵害するおそれがありそうな遺贈や贈与を発見した場合には、とりあえず遺留分侵害額請求の意思表示を内容証明郵便でしてしまっておくことをお薦めします。
また、具体的な遺留分侵害額の計算自体が極めて複雑ですし、令和元年7月1日の改正法施行日前に開始した相続については原則として旧法が適用されるなど(附則第2条)法改正も絡むので、遺留分が侵害されている可能性を感じられたら弁護士へ相談してください。

生前贈与と呼ばれるものも、法的には単なる贈与契約です。これが特別受益に該当すれば相続分が変わりますし(民法903条)、遺留分侵害額請求の対象になる(民法1046条)など、生前贈与は、相続に関して大きな影響を与えます。相続紛争では、必ず生前贈与の事実が主張されるといっても過言ではありません。明らかに高額な財産の移動があれば、贈与自体が争いになることは少ないですが、被相続人の預貯金口座から50万円から100万円程度の出金がされている場合は、相続人のために利用されたという客観的証拠がないことが多く、贈与であることを認めさせることは容易ではありません。被相続人と疎遠になっていたり、一部の相続人に世話を任せていたのでは、使途を把握できなくて当たり前だと思います。被相続人の財産の流れを記録することで無用な紛争を予防できるので、面倒かもしれませんが、被相続人と積極的に関わり、財産を把握されるようにして下さい。

「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価値から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、民法900条から902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」(民法904条の2第1項)、「前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。」(民法904条の2第2項)と規定されており、特別の寄与については、相続分を増やすことを認めています。通常は、遺産分割協議の中で話し合われ、話し合いで解決できない場合には遺産分割調停・審判で解決することになります。
特別受益と並び、寄与分は紛争になることが多い主張です。一般人の感覚からすれば、世話をしたことで寄与分が認められると思うかもしれませんが、実際には「特別の」寄与だと裁判所が認めることは多くありません。
なお、民法改正によって、共同相続人以外で特別の寄与をした者があれば、その者に対して特別寄与料が認められるようになりましたので(民法1050条)、今後は、共同相続人以外に相続人の世話をした方からの相談が増えることが予想されます。
相続紛争を多く経験した弁護士であれば、相続紛争を予防する観点から遺言書の作成など具体的に提案してくれますし、いざ相続が開始した場合には、相続人調査や相続財産調査などを行い、客観的資料や法的主張を整理したうえで、無用に紛争化しないよう交渉をしてくれます。弁護士が関与すれば紛争が大きくなると勘違いされている方が多いかもしれませんが、的確な資料をもとに法的主張を行うことでかえって紛争化しないことも多いものです。また、相続紛争は、裁判や審判より協議や調停で柔軟に解決しているものの方が圧倒的に多く、うまく交渉や調停を進める交渉力も重要ですので、経験のある弁護士へ依頼することのメリットは大きいと思います。相続法分野について民法が改正され、改正法の知識も不可欠ですから、弁護士の力を借りるべきだと思います。

CASE01
弁護士の仕事は、生の事実を法的に構成して考えることですから、難しく考えずに弁護士へ事情をお話いただくのが一番です。きっと、相続問題を多く扱っている弁護士であれば、相談に来られた方に対して、複雑な法律をわかりやすく説明し、具体的にどう進めるかについても説明するはずです。
遺産の額からして、弁護士へ依頼した場合に費用対効果が見合わない場合もあるかもしれませんが、費用対効果が見合わないということで納得して終われるのではないでしょうか。
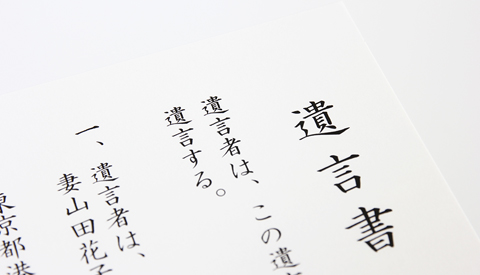
CASE02
遺言書があるとしても、遺言の有効性や遺留分の問題など、法的に検討しなければならない事柄は山積みです。

CASE03
相続放棄には相続開始を知った時から3か月という期間制限がありますから、期限内に相続放棄ができるか不安に思いつつ、ご自身で手続きをすることは大きなストレスでしょうし、いちいち戸籍を取ったり、家庭裁判所へ書類を提出したりするという作業は面倒なものです。また、法定単純承認になってしまっては相続放棄ができなくなりますので、何をしていいのか、何をしてはいけないのか迷われると思います。
費用はかかりますが、弁護士などの専門家へ丸投げしてストレスから解放されるというメリットは大きいと思います。

CASE04
遺産分割協議がうまく進められていないのは、主張が法的に整理できていないことが原因であることが多いと感じます。色々資料が出されていたとしても、何が言いたくて当該資料が出されているのかさっぱりわからないということも多く、法的に意味のない主張が大々的に展開されれば、無駄に時間と労力がかかります。
相続案件を多く扱う弁護士であれば、相手の主張はだいたい予想できますし、何が重要な資料なのかも判断ができますので、無駄な主張に付き合うことなく、大事な部分だけを的確に主張して進めてくれます。あくまで私の印象に過ぎないかもしれませんが、早期に適切かつ分かりやすく資料を整理し主張を展開すれば、裁判所の調停委員は、相手方を説得しようとしてくれます。
01
お問い合わせ
02
ご予約
03
来所相談
04
ご契約
05
解決
来所法律相談30分無料 相続のお悩みなら私たちにお任せください。
まずは専任の受付スタッフが丁寧にお話をお伺いいたします。
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
裁判例 01
【東京高判平成22年7月15日判例タイムズ1336号241頁】
(事案)
司法書士立会いの下で作成された公正証書遺言(遺言者A 87歳)について、当該公正証書遺言の作成自体はAの意思に基づいて作成されたことを認めつつ、認知症の症状が進行し医師に認知症と診断されたことや介護老人保健施設への入所を続け、当該遺言時に認知症が診断時よりも進行していたものと認められることなどから認知症により遺言能力を欠くとし、Aの受け答えなどから遺言の能力があると感じた司法書士2名が立ち会って作成された公正証書遺言だとしても、これによって認定は妨げられないとした事案。
(解説)
遺言を作成するのは高齢者であることが多いなか、遺言の増加と共に、遺言能力が争われる事案も増加しています。もっとも、遺言能力と一言にいっても明確な判断基準があるわけでなく、裁判所は、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するに必要な判断能力(意思能力)を遺言能力と解し、遺言内容に応じて遺言能力を相対的に判断し、遺言能力が認められない場合に、当該遺言を無効と判断している状況です。判断手法が決まっているわけではないものの、精神医学的な疾患の存否や内容、程度を医師の診断書や診療録、公証人や立会人、同居人、担当医の供述などをもとに認定しつつ、当該遺言内容の複雑さ、当該遺言に至る経緯、生活状況、遺言をする動機や理由の有無、当事者の関係等といった事情を踏まえ、個別具体的に判断している状況です。
本件においても、平成17年12月16日に公正証書遺言が作成された際の遺言能力が争点になっていたところ、関係者の供述や訪問看護記録や居宅サービス計画書、診療情報提供書、診療録の記載内容などをもとに、平成11年ころからAは家族に対する暴力や暴言が目立つようになったのち、平成15年11月ころには現金や通帳を管理など金銭管理ができなくなり、平成16年ころには近隣知人のかをもわからず、昼夜逆転の生活、妄想被害を訴えるなどの症状が現れ、平成17年5月には長谷川式スケールで20点、平成18年9月には11点となっているなどの事実から認知症の程度を推認しつつ、同居し介護にあたった相続人に財産を一切残さないという特異な遺言の内容などを踏まえ、遺言能力が無いとしており、同様の手法で判断されているといえます。本件が特徴的なのは、公正証書遺言作成に立ち会った司法書士が、Aに遺言能力があると感じたとしても、遺言作成日に初めて会ったに過ぎず医師や介護施設職員から聴取しておらず判断に影響しないとした点です。
裁判例 02
【最判平成30年10月19日民集72巻5号900頁】
(事案)
被相続人が夫で、相続人が妻Aと子4名(B、C、D、E)であったところ、遺産分割調停の間に、AとEがCに対して相続分を譲渡して調停手続きから脱退し、残るB、C、Dで遺産分割調停が成立したが、その後、AはCに全財産を相続させる公正証書遺言を残し死亡した(相続人A、B、D、E)ため、BがCに対して遺留分減殺請求をした。この事案では、亡夫の相続におけるAのCに対する相続分の譲渡が、亡Aの相続において、遺留分算定の基礎となる財産額に算入すべき贈与(民法1044条、同903条)といえるかが争点となり、最高裁は、相続分の譲渡は、譲渡に係る相続分に含まれる積極財産及び消極財産の価格等を考慮して算定した当該相続分に財産的価値があるとはいえない場合を除き贈与にあたるとし、これを肯定しました。
(解説)
相続分の譲渡は、共同相続人間でされる場合もあれば、共同相続人と第三者でされる場合があり、本件は共同相続人間でなされたものでした。下級審においては、共同相続人間の相続分の譲渡に関して、肯定するものと否定するものに分かれていたところ、本判決により「贈与」(民法1044条、同903条)に該当すると統一されたものだと解されます。今後は、共同相続人間で相続分の譲渡が「贈与」に該当することを前提に、相続分の譲渡をしつつ持ち戻しの免除の意思表示をするか、そもそも相続分を譲渡せずに遺産分割で多く取得させるか検討すべきことになります。

相続は、亡くなった方の意思を尊重してなされるべきで、相続が開始してから相続人が考えるものではないと思います。相続の話をタブー視せず、是非、親族で話をする機会を作ってみてください。また、相続が開始してしまった時には、相続放棄の期間制限や相続税の申告期限もあるので、できるだけ早く相続について把握されるようにして下さい。
法的にややこしい分野ではありますが、弁護士など法律の専門家にご相談いただければ、きっと、わかりやすく具体的な説明を聞くことができると思います。
弁護士が関与することで紛争化するとお考えかもしれませんが、相談をしただけでは紛争になりませんし、弁護士に相談することで頭を整理して、しっかりと意見を言えるようになるのではないでしょうか。もっと、弁護士をうまく活用していただきたいものです。

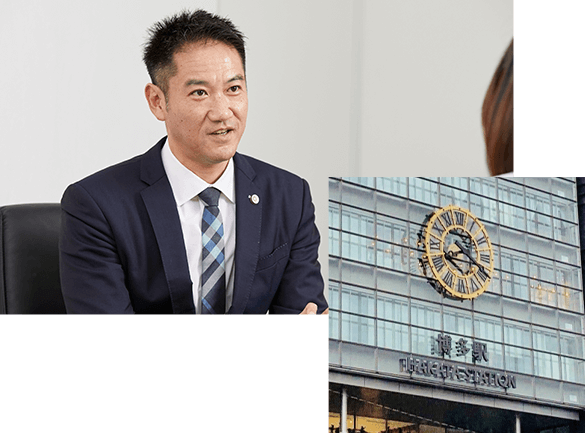
平成29年の司法統計によれば、福岡家庭裁判所での遺産分割事件は512件で全国7番目であることから、全国的にみて相続紛争が多い地域といえ、多くの方が相続問題に頭を悩ませていることがわかります。
弁護士法人ALG&Associatesでは、これまで1200件を超える相続案件をご依頼いただいております(相談だけの方は含めておりません。)ので、安心してご相談、ご依頼下さい。事情を丁寧にお聞きさせていただいたうえで、わかりやすくご説明させていただきます。
来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。
※30分以降は、30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談となります。
※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。
※当日、当法人にご依頼いただきました場合、延長された法律相談は無料とさせていただきます。
延長をご希望された場合でも他のご予約の関係で対応できないケースもございますのでご了承下さいませ。