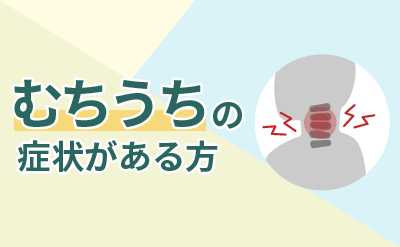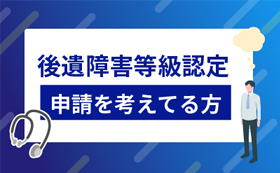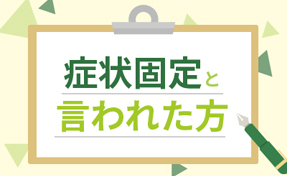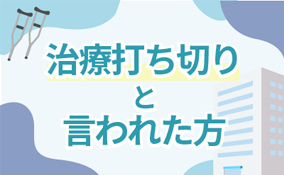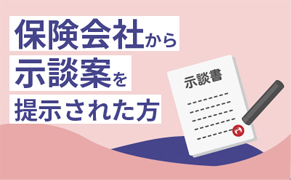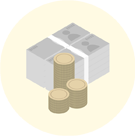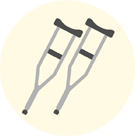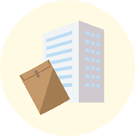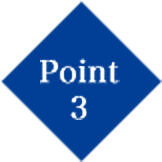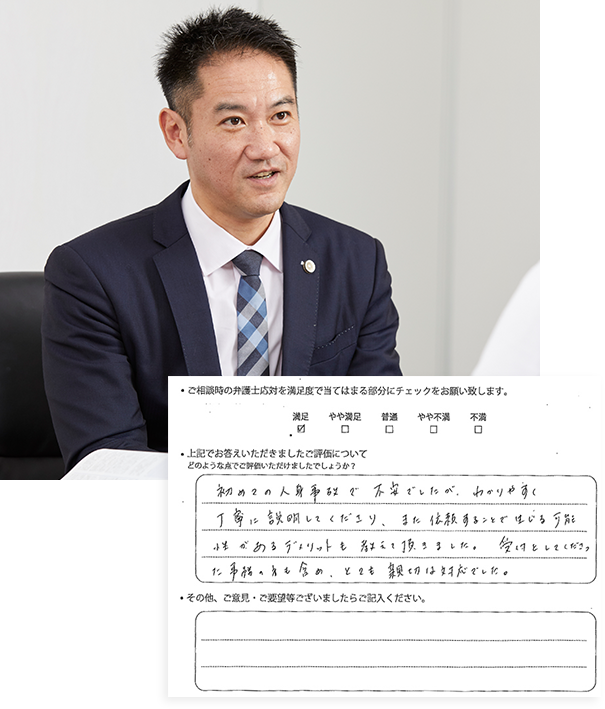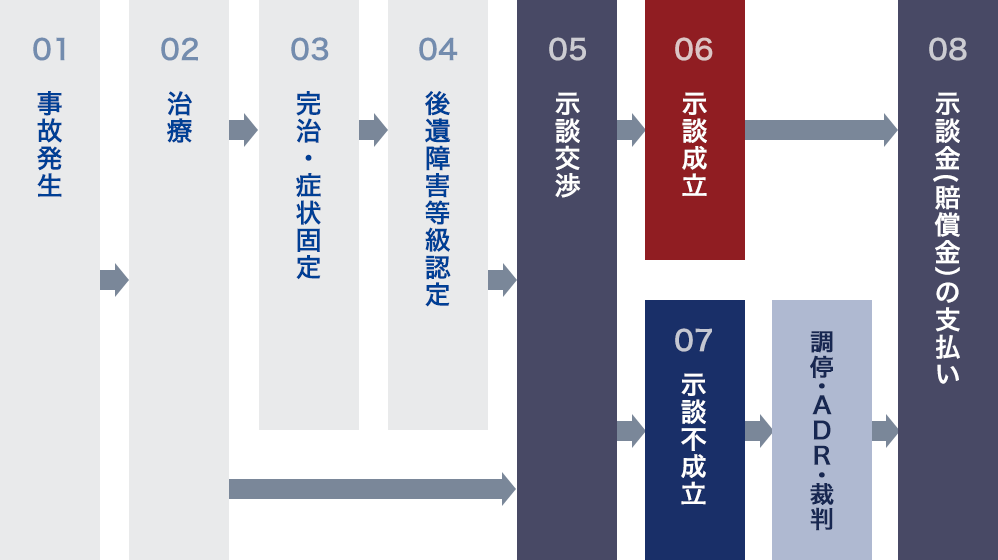
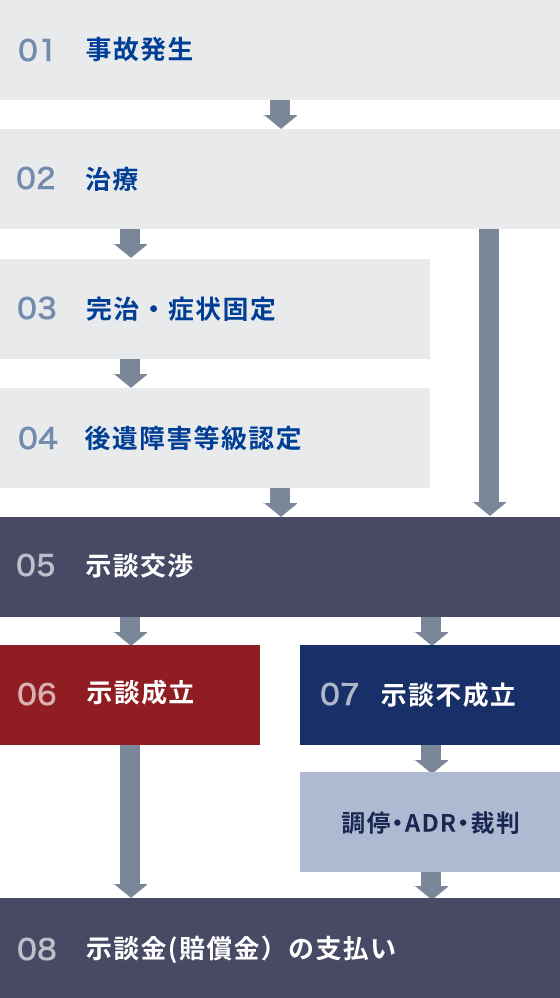
加害者側が自動車保険(任意保険)に加入していれば、通常、加害者側の保険会社の担当者が交渉窓口になります。
ほとんどの被害者は、交通事故に遭うのが初めてでしょう。保険会社の担当者は、交通事故対応を仕事にしているプロです。交通事故の素人とプロが交渉するのですから、被害者側が不利なことは一目瞭然です。保険会社は、保険金が少なければ少ないほど利益が多くなりますので、保険会社は何とか少ない額で示談しようとしてきます。
被害者側としては、知らずに不利な内容で示談することのないようにしなくてはなりません。


保険会社が提示してくる金額は妥当なのか
結論から言うと、私は、保険会社から妥当な損害額提示を受けたことはほとんどありません。
被害者側に過失があり、過失割合を考慮すれば、重過失減額されない自賠責保険の内容で解決する方がお得な場合や軽微な事故で明らかに必要性が認められないような長期間の治療費を認めている場合、資料が不十分であるにもかかわらず長期間休業損害を認めてきているような場合など、総合的にみれば妥当な場合は時々ありますが、これを見分けることは簡単ではありませんので、保険会社からの提示額は、基本的には妥当でないと考えておいていただいてよいと思います。


治療の打ち切りを打診されることも
軽微事故の場合、保険会社は早期に治療費の支払いを打ち切ってきます。
保険会社は、最近、軽微な追突事故であれば、治療費を1~3か月で打ち切ってきているように感じます。担当者にもよるので保険会社でひとくくりにはできないとは思いますが、ある保険会社は、明らかに支払いに厳しくなっています。たとえ主治医が治療を続けるべきだといっても、保険会社が治療費を支払わなくなることはよくあることで、被害者は、自費で継続通院するか否か判断を迫られ、多くの方は治療を終了されているようです。
事故態様や治療経過からすれば、後遺障害等級の認定がされる可能性が高く、健康保険を使ってでも治療継続すべき場合もありますので、保険会社の言いなりになるかどうかは慎重に判断する必要があります。